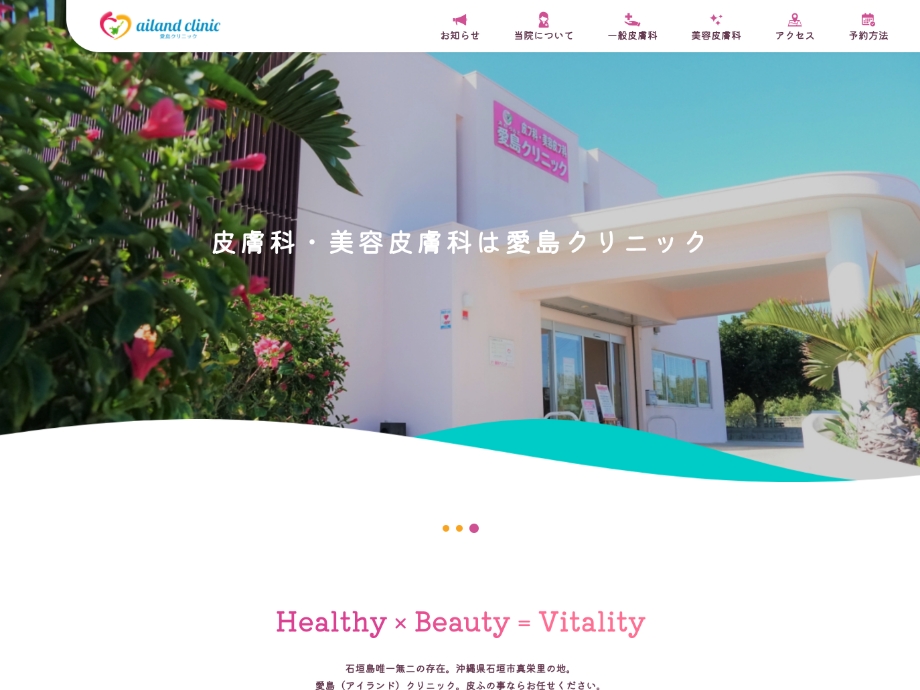ホームページ制作会社の選定は非常に難しく、支援先やパートナーのコンサルティング会社さんなどからもよくご相談いただきます。
ここでは失敗する可能性が高い要因を不定期で更新していきますので、これから作る方や過去失敗した方の参考になれば幸いです。
15年以上Web業界で大手・中小企業・行政のホームページを制作してきました。
Web制作の相談対応件数は、簡単なものも含めると3,000件以上になります。
ホームページ制作に必要なスキルは全て保有し、デジタル人材の採用・教育経験もあります。
Web制作だけでなく、デザイン事務所等の紙媒体デザイン(グラフィックデザイン)出身のため、デザインがもたらすブランディングも重要視しています。
【保有しているスキル・知識】
『企画・提案』、『設計・契約』、『構成制作(ワイヤーフレーム)』、『デザイン』、『コーディング』、『システム構築』、『マーケティング(SEO対策、MEO対策、Web・SNS広告など)』、『集客・採用コンサルティング』
【一部の参考実績・経験】
『大手コンペディション提案・採用実績』、『官公庁Web制作経験』、『デジタル人材の新卒・中途採用/教育経験』、『人事評価制度の構築経験』、『事業会社でのWeb制作部署立ち上げ経験』、『開業・開院の支援』など
本当に質の高いホームページ制作を行うには、担当者に以下4軸が高いレベルで必要になると断言できます。
・Webデザインスキル
・システム構築知見
・Webマーケティング知識(SEO対策、MEO対策、Web広告、SNS広告など)
・コミュニケーション能力(専門用語の噛み砕きや進捗報告など)
新卒教育経験もありますが、高品質なものを提供できるレベルに育てるには最低3年以上は実務経験が必要です。
メイン担当が経験3年以下の場合は、あなたのホームページ制作の一部は研修材料にされてますので、新人担当や新卒採用している会社には気をつけてください。
また最近は職業訓練校で学んだ方や独学で副業を始めた方がWebデザイナーを名乗り、格安制作して失敗する事例も多くなっています。
『ホームページのデザイン・構築』と『Webマーケティング』の豊富な実務経験がある人に依頼できれば失敗することはほぼありません。
ホームページ制作の流れは、設計→お見積もり→契約→制作→管理・メンテナンスです。
一番失敗したと聞くケースが、流れの前半にある『設計』と『お見積もり』で話す担当者がホームページ制作に関連するスキルに乏しい営業マン・コンサルだった場合です。
デザインや構築などの土台となるスキルを有している担当だとメンテナンス性に優れた無駄のない構造設計が出来るかが変わってきます。
担当者がスキルを有している安心感を他業界で例えると、注文住宅を建てる際に設計士と契約ができるイメージです。
担当が営業マン・コンサルだと競合他社を表層で真似する不適切な設計となり、都度発生する追加改修に倍以上の作業費が必要な場合があります。
また深く設計していないため、契約当初に約束したことが実は技術的に難しくて反映されていないという失敗にも繋がります。
特に注意したいのがこの業界で営業マンは自身を「営業」とは名乗っていません。
『Webコンサルタント』『Webディレクター』『○○アナリスト』『○○プランナー』などを名乗ります。
担当の保有スキルや経歴の確認は必ず行ってください。
一般の方が営業マンと見抜くのは難しいのですが、相談した際に「制作に確認します」と時間がかかったり、過去の事例しか紹介できない担当は警戒してください。
あと営業マン・コンサルはスーツを好んで着用している傾向があります。優秀なIT人材(スキルを保有した設計・契約からできる人)はスーツを好まないため、スーツを強要される営業主体の会社には長く残らないでしょう。
ホームページ制作において、間に入る営業マン・コンサルの存在は、お客様にとって一番不要なコストと覚えておいてください。
この業界のスキル保有者は話すのが苦手な方が多いですが、話しやすいからといって平気でオーバートークする人には騙されないように気をつけましょう。
フリーランスや副業で登録している方が多く、比較的低価格で依頼することができますが、品質や実力の差が大きく見抜きづらいため注意が必要です。
これらのサービスは実績がないとなかなか受注できません。そのため『実績作り』のために格安で提供している方が散見されます。
この格安で作ったホームページは、一般の方からは綺麗に見えてもプロが見たら中身や設定がボロボロのケースがほとんどです。
利用した方からの意見や弊社チェック後の問題では以下のようなものがありました。
・検索対策(SEO)が考えられていない
・集客やブランディングなどのビジネス観点が足りず作品作りの感覚に近い
・作って終わりの前提でメンテナンス性や拡張性が非常に低い
・社会競争を経験していない人が多いためか、責任感やビジネスマナーが足りない
・オリジナルと言いながら、テンプレートを使い回している
もちろん、中には経験豊富で優秀な方もいますが、すでに人気なため、納期が長く、価格が高かったりします。
ホームページ制作会社に依頼するのと変わらなくなってきますので視野を広げて検討されるのがおすすめです。
経験上、大企業は避けた方がいいです。
組織が大きいと以下のような様々なコストが制作費に上乗せされています。
・立派なオフィス代(地代・光熱費・通信費など)
・必要以上に多い間接部門の人件費(事務スタッフや受付・お茶汲み要員)
・新卒採用コストや研修費
・従業員への手厚い福利厚生
その代わりノウハウがあるんじゃない? と思う方も多いですが、人材が流動的で意外に経験の浅い方が多いです。
それ故にノウハウとトレンドの取捨選択ができず、中途半端な提案が多い印象です。
また数が必要になるため、短い期間で制作を終わらせたがります。
デザインの確認を急がされたり、修正受付1回までと言われるなど、こだわった制作ができません。
普通のオフィスや体制で信念を持って制作している有名企業も稀にあり、そちらはおすすめです。
よっぽど数名の制作会社の方が納得いくものができるかと思います。
ホームページ制作に失敗したお客様からの相談の際では、「失敗した」「騙された」「納期が守られない」「デザインがいまいち」「集客できない」「最終的に予算をオーバーした」「管理費が高い」などネガティブワードがよく出てきます。
こだわりたいポイントをしっかり伝え、お客様ごとに異なる成功を定義し、契約前にホームページ制作会社と共通認識とすることが大切です。
目標設定の例としてわかりやすいものは、問い合わせ数、会員登録数、資料請求回数、来店数、注文数、求人エントリー数などが挙げられます。
あとはホームページに訪問してくれたユーザーの行動を指標とした、滞在時間、直帰率、閲覧ページ数などもあります。
ホームページには、ポータルサイト、ブランドサイト、コーポレートサイト、マーケティングサイト、ECサイト(通販)、採用サイト など達成したい目標ごとに種類が存在します。
それぞれに必要な機能や制作ポイントが異なり、進行中に工夫することでホームページ制作の失敗要因を排除します。
契約するホームページ制作会社の部署や課が”営業”と”制作”の部署に分かれており、評価制度が定量(粗利・数字)重視の場合気をつけてください。
この場合、お客様の温度感と制作担当との温度感・熱意が乖離してトラブルになります。
例えば、お客様が100万円でホームページ制作を依頼した場合、営業部署が7割以上近くを中抜きし、制作の部署が3割しかないということになります。そうなると制作の部署には30万円しか入らないので、納品優先の手抜き対応となりトラブルとなります。
そして仕組みとして会社からも評価されないので優秀なIT人材は会社を去ります。
実際にこのような会社は存在し、歴史のある会社や人数が多い会社に多いので気をつけてください。
環境・制度を作る経営陣(代表取締役や役員)がIT知識に乏しいと、IT人材が本当に働きやすい環境を作れることができず会社に残ってくれません。
ホームページ制作は会社の過去の実績よりも優秀なIT人材が担当してくれるかが成功の鍵になります。
他にもお伝えたいこともあるのでまた更新していきます。